top of page


【建設業許可】取得後にやるべきことまとめ|変更届・決算報告・技術者配置
建設業許可を取得してひと安心…と思っていませんか? 実は、許可取得後には毎年の決算変更届や各種変更届の提出、技術者の配置義務、標識掲示など、継続して守るべきルールがあります。 これらを怠ると更新や経営事項審査等の申請に影響したり、場合によっては処分対象になる可能性もあるので、注意しなければなりません。 本記事では、許可取得後にまず押さえておくべき重要ポイントを整理します。 💡この記事のポイント ●建設業許可を取得した後も、毎年・随時の手続きが発生する ●役員変更や専任技術者の交代などは「変更届」の提出が必要(期限14日以内のものもある) ●決算終了後4か月以内に「決算変更届」の提出が義務付けられている ●現場には主任技術者・監理技術者の適正な配置が必要 ●請負契約では一括下請負禁止や不当な取引の禁止などの規定を守る必要がある ●営業所・現場での許可票掲示、帳簿備付け・図書保存義務がある ●届出漏れは更新や経営事項審査の際に必ず確認される ●許可を維持するには、継続的な管理体制が不可欠 ▼目次 1. まず押さえるべき「届出関係」 (1) 各種変更
3 時間前


【経営事項審査】Z(技術力)で点数を上げるには?|評価の仕組みと戦略的な改善ポイント
「経審の点数を上げるには施工管理技士の資格を取った方がいい」とよく言われますが、実際にZ点はどの程度変わるのでしょうか。 経営事項審査における「Z(技術力)」は総合評定値の25%を占める重要な評価項目です。 しかし、単に資格者を増やせばよいというものではなく、業種選択や雇用要件、元請完成工事高との関係を踏まえた検討が必要です。 本記事ではZ点の評価仕組みと、戦略的に改善を考えるためのポイントを整理します。 経審の点数について基本的なことから確認したい方は、以下のリンク記事を先にご確認ください。 経営事項審査(経審)の点数を上げる方法|P点の仕組みと3つの考え方 ▼目次 1 . 経営事項審査(経審)における「Z(技術力)」の位置付け 2. Z点(技術力)を構成する2つの評点 (1) 技術職員Z1 (2) 元請完成工事高Z2 3. 加点対象になる技術職員とは (1) 資格要件 (2) 恒常的雇用関係と常勤性 4. 最後に 経営事項審査(経審)における「Z(技術力)」の位置付け 経審の点数は、5つの評価項目で構成されています。...
3 日前


【大阪府】産業廃棄物収集運搬許可の取り方|要件・講習・申請のポイントを解説
「産業廃棄物収集運搬の許可を取って業務の幅を広げたい」と考える建設業者や便利業の方は多いでしょう。 しかし、講習の予約、車両要件、財務基準、都道府県ごとの取扱いなど、実際の取得までには整理すべきポイントがいくつもあります。 本記事では、大阪府で産業廃棄物収集運搬許可(普通)を取得するために必要な要件、講習、申請書類、審査の流れを実務目線で解説します。 ▼目次 1. 整理すべき3つのポイント(立場・エリア・品目) (1) どのような立場で収集運搬に関わるのか (2) 産業廃棄物をどこで積み込み、どこに運ぶのか (3) どの種類(品目)の産業廃棄物を運ぶのか 2. 大阪府の産業廃棄物収集運搬許可の要件 (1) 産業廃棄物に関する知識があること (2) 欠格要件に該当しないこと (3) 運搬車両・容器があること (4) 経理的基礎があること 3. 申請書類と事業計画作成のポイント 4. 申請先・審査期間・スケジュール感 5. 最後に 整理すべき3つのポイント(立場・エリア・品目) 許可の要件等よりも先に、どのような立場でどこからどこに何を運ぶのか
5 日前


【建設業許可】取得・更新にかかる費用はいくら?自力申請と依頼した場合の総額を比較
建設業許可を取得するには、法定費用だけで9万円~15万円が必要です。 さらに、5年ごとの更新や業種追加の申請、公共工事入札を行う場合の経営事項審査など、状況に応じて追加費用が発生します。 では、自分で申請した場合と行政書士へ依頼した場合では、総額や負担はどれくらい違うのでしょうか。 本記事では、建設業許可の取得から維持、入札までにかかる費用の内訳と総額の目安を整理し、自力申請と依頼した場合の違いについても解説します。 ▼目次 1. 建設業許可は取得した後も費用がかかる (1) 新規申請の際にかかる費用 (2) 業種追加申請の際にかかる費用 (3) 更新申請の際にかかる費用 2. 公共工事の入札まで行う場合はさらに費用がかかる (1) 経営状況分析の際にかかる費用 (2) 経営事項審査の際にかかる費用 (3) 電子入札の際にかかる費用 3. 行政書士に依頼した場合はどれくらいの費用がかかるのか 4. 最後に 建設業許可は取得した後も費用がかかる まず、新規で申請する際に費用がかかり、許可を取得した後にも業種の追加や許可の更
2月14日


【建設業許可】専任技術者になれる人の条件(資格・実務経験)を解説
「建設業許可を取得するには何か資格が必要ですか?」このようなご質問をよくお受けします。 建設業許可は経営能力、技術力、財産的基礎、適格性等、いくつかの許可要件を満たさなければ取得することができません。 この中の「技術力」というものが 、 まさに資格に関係する許可要件で、資格を持っている人を 営業所技術者等(専任技術者) として配置できるかどうかが問われます。 しかし、必ずしも資格が必要というわけではありません。 一部業種を除きますが、資格がなくても一定の経験があれば 営業所技術者等(専任技術者) の要件を満たすことができます。 この記事では、 営業所技術者等(専任技術者) に必要な資格や経験、その他求められることについて詳しく解説しています。 ぜひご参考にしていただければと思います。 ▼目次 1. 許可要件の中での営業所技術者等(専任技術者)の位置づけ (1) 営業所技術者等(専任技術者)は技術力を表す重要な許可要件 2. 営業所技術者(専任技術者)に必要な資格とは (1) 営業所技術者等(専任技術者)になり得る国家資格等の一覧 3....
2月13日


建設キャリアアップシステム(CCUS)|制度の全体像と立場別に確認すべきポイント
「 建設キャリアアップシステム(CCUS) 」とは、建設業技能者の現場ごとの就業履歴、保有資格、社会保険加入状況等を登録・データ蓄積し、客観的に技能者を評価できる仕組みのことです。 国が主導し、2019年4月から本格的に運用されています。 現時点では「 建設キャリアアップシステム(CCUS) 」の登録は任意( 外国人の受け入れを除く )ですが、以前から発表されているとおり、近年中には民間工事、公共工事を問わず、登録が完全義務化されることになるでしょう。 すでに 建設キャリアアップカード がなければ入れない現場が増えていることを実感している方も多いのではないでしょうか。 建設キャリアアップシステム(CCUS)は、事業者・技能者・一人親方など、立場によって登録内容や手続きが異なります。まずは、ご自身の立場に近いものをご確認ください。 ▶ 技能者の方 建設キャリアアップシステムの技能者登録|詳細型と簡略型どちらを選ぶべき? ▶ 一人親方の方 一人親方の建設キャリアアップシステム登録|事業者登録は必要?技能者登録との違い ▶ 建設キャリア
2月9日


建設業許可を早く取得するには?大阪府で最短取得するための実務手順
建設業許可なしで請け負うことができる軽微な工事(請負金額500万円未満の工事)であっても、許可のない業者は受注機会が減少傾向にあります。 工事規模に関わらず、下請に建設業許可の取得を求める元請が増えているからです。大手は以前からそのスタンスですが、中小ゼネコン等にも広がってきているのです。 建設キャリアアップシステムの登録を求められることも増えており、建設業許可+建設キャリアアップシステム登録が珍しくない状況になりつつあります。 近年の大阪府のデータを見ても、建設業許可業者が増加傾向にあることがわかります。 40,042者(2022年)→40,376者(2023年)→41,046者(2024年)→41,645(2025年) 受注機会を逃さないように、より大きな工事を請け負えるように、1日でも早く許可を取得したいとお考えの方も多いのではないでしょうか。 この記事を読むと、大阪で建設業許可を1日でも早く取得するために何をすべきかが分かります。 ぜひご参考にしていただければと思います。 ▼目次 1. 建設業許可の取得を早めるために知っておくべきポイント
2月5日


特定建設業許可とは|必要になるケース・ならないケースの判断基準を解説!
建設業許可には一般建設業許可と特定建設業許可があります。 建設業許可をはじめて取得する際に、いきなり特定建設業許可を取得するケースはあまり見られません。 2025年3月時点で一般建設業許可を取得している業者は458,055業者、一方で特定建設業許可を取得している業者はわずか49,739業者しかありません。 許可要件が厳しく、クリアできない建設業者が多いのはもちろん、一般建設業許可でも特に支障がない建設業者が多いのが実情です。 本記事では、特定建設業許可の許可要件や注意点、一般建設業許可との違いを詳しく解説しています。 ぜひご参考にしていただければと思います。 ▼目次 1. 一般建設業許可・特定建設業許可は許可の区分の1つ 2. 大規模な工事は特定建設業許可がなければ請け負えない? (1) 判断基準は「工事の規模」ではなく「請け負う立場」と「下請への発注金額」 (2) 下請けへの発注金額にはどこまでが含まれる? (3) 特定・一般どちらも請負金額自体には制限がない 3. 特定建設業許可は一般建設業許可に比べて許可要件が厳しい (1)...
2月5日


建設業許可「舗装工事業」完全ガイド|工事内容・許可要件等を徹底解説!
舗装工事業は、道路や構内、敷地内通路などの地盤面を舗装する工事を専門とする建設業の業種です。 国道・都道府県道・市町村道などの道路舗装のように公共工事として発注されるものと、商業施設や工場、集合住宅・戸建住宅の駐車場舗装などの民間工事があります。 舗装工事は、施工内容が比較的明確な一方で、「どこまでが舗装工事業の範囲に含まれるのか」「どの資格が必要なのか」といった点で、判断に迷う場面も少なくありません。 本記事では、舗装工事業の工事内容、建設業許可が必要となるケース、専任技術者の要件や申請手続きについて、行政書士が実務目線で整理・解説します。 💡この記事のポイント ●舗装工事業は、道路・構内・敷地内等の地盤面を舗装する専門工事業種 ●公共工事のイメージが強いが、駐車場舗装など民間工事も広く存在する ●500万円以上の舗装工事を請け負う場合は建設業許可が必要 ●舗装工事業は指定建設業であり、特定建設業の要件に注意が必要 ●専任技術者は施工管理技士等の資格、または一定の実務経験が必要 ▼目次 1. 舗装工事業の位置づけ 2. 舗装工事業に該当する工
2月3日


建設業許可「水道施設工事業」完全ガイド|工事範囲・管工事との違い・許可要件
水道施設工事業は、上水道・下水道といった公共インフラの根幹を担う専門工事業種です。 一方で、管工事業や土木一式工事との区分が分かりにくく、許可の要否や業種判断を誤り、入札段階で支障が生じるケースも見受けられます。 本記事では、水道施設工事業の工事範囲、管工事・土木工事との違い、建設業許可が必要となるケース、専任技術者要件や申請手続きまでを国交省ガイドラインや自治体の入札実務を踏まえて、行政書士が実務目線で解説します。 💡この記事のポイント ●水道施設工事業は、上水道・下水道など公共団体が設置・管理する水インフラ施設を対象とする業種 ●取水・浄水・配水施設、下水処理場内の処理設備は水道施設工事に該当 ●建物敷地内の給排水配管は管工事、公道下の下水道本管工事や造成は土木一式工事に区分される ●水道施設工事は公共工事が中心で、実務上500万円未満の工事はほとんどなく、原則として建設業許可が必要 ●専任技術者は土木施工管理技士や技術士などの資格、または一定の実務経験が求められる ●業種判断や証明資料の不備により、許可取得でつまずくケースも多いため、事前
1月27日


建設業許可「管工事業」完全ガイド|工事範囲・許可要件・申請実務を解説
管工事業は、空調設備・給排水設備・衛生設備など、建物の機能を支える設備工事を担う専門工事業種です。 一般住宅から商業施設、工場、公共施設まで施工対象が幅広く、建設業の中でも完成工事高・許可業者数ともに多い業種として位置づけられています。 一方で、エアコン設置工事や配管工事など、他業種と工事内容が接する場面もあり、業種区分や許可の要否を正しく理解しないまま工事を行っているケースも見受けられます。 本記事では、管工事業の位置づけ、該当する工事内容、建設業許可が必要となるケース、専任技術者の要件や申請手続きまでを、行政書士が実務目線でわかりやすく解説します。 💡この記事のポイント ●管工事業は建物設備を支える専門工事業種 ●エアコン設置工事は原則として管工事に該当 ●電気工事が付帯工事として発生することが多い ●電気工事を行う場合は資格・電気工事業登録が必要 ●指定建設業のため特定建設業の要件には注意が必要 ▼目次 1. 管工事業の位置づけ 2. 管工事業に該当する工事とは 3. 管工事業と他業種との関係 4. 管工事業で建設業許可が必要となるケース
1月21日
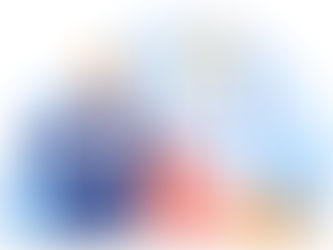

建設業許可「消防施設工事業」完全ガイド|工事内容・許可要件・申請手続を実務解説
消防施設工事業は、建物に設置される消防用設備等を施工・改修することを目的とした専門工事業種です。 消防法と密接に関わる業種であり、高い専門性と資格要件が求められることから、建設業許可を取得している業者は全業種の中でも非常に少ないのが特徴です。 消防施設工事は、火災報知設備や消火設備、避難設備など、人命や財産を守るために法令上設置が義務付けられている設備を対象とするため、需要がなくなることはありません。 本記事では、消防施設工事業の位置づけ/どのような工事が消防施設工事に該当するのか/許可取得の要件と手続きについて、行政書士が実務目線で解説します。 💡この記事のポイント ●消防施設工事業は消防用設備等を設置・改修する専門工事業種 ●電気工事や管工事は付帯作業として含まれる ●業種判断に迷うことは実務上ほとんどない ●500万円以上の消防施設工事には建設業許可が必要 ●専任技術者は消防設備士の資格が必須 ●許可取得により安定した受注が期待できる ▼目次 1. 消防施設工事業の位置づけ 2. 消防施設工事業に該当する工事とは 3. 消防施設工事業で建
1月17日
bottom of page